 |
 |
| 【山記録】 | ||
| 日時・天候 | 2005年03月06日(日)曇り/晴 | |
| 山名・標高 | 清水頭(1095m)/雨乞岳(1238m) | |
| 山域 | 鈴鹿 | |
| コースタイム |
駐車地(08:56)〜尾根出会(09:45-9:55)〜清水頭(11:00)〜鞍部で昼食(11:15-12:00)〜雨乞岳(12:45)〜南雨乞岳(14:30)〜シャクナゲ尾根口(14:42)〜駐車地(15:40) ●総タイム7時間16分(休憩00分程度含む) |
|
| 距離/累積高度差 | 沿麺距離 キロメートル 累積高度差(+m -m) | |
| 団体名等 | Gisuzuka30数名ほど | |
| 【軌跡ログ】 |
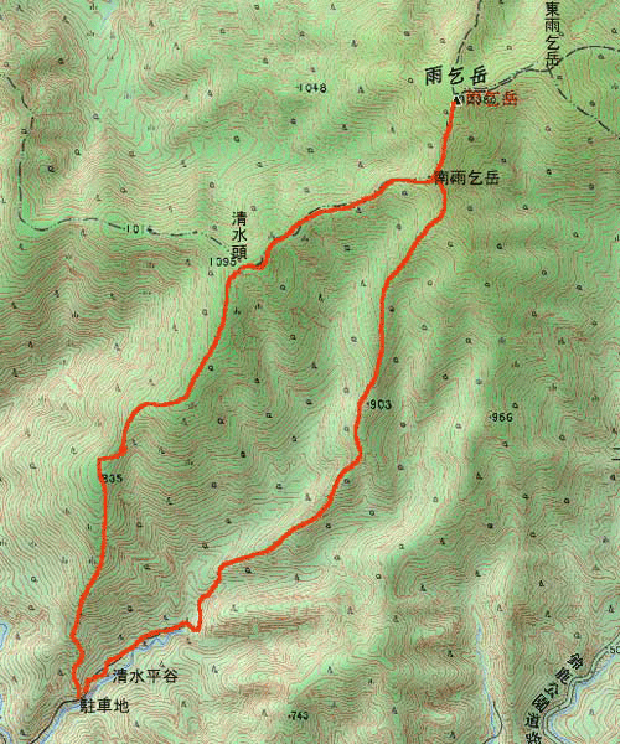 |
| 【足跡】 |
鈴鹿の山ハキング百選(西内正弘著)の91にある清水頭南尾根から雨乞岳南尾根を経て清水ケ平谷の周回コースを歩く。国道477号鈴鹿スカイラインは現在通行止につき鈴鹿トンネルを過ぎ猪鼻から、国民宿舎かもしか荘へ来て国道477号へ入る。間もなく開通するのであろうか日曜日というのにかもしか荘の少し先で道路の補修工事をしていた。 かもしか荘から2キロほど先の深山橋を左折れ白倉谷林道に入る。案内本には「深山橋東から4キロ先で橋の架かる分岐で右折れして橋を曲がる。それから先は清水ケ谷に沿った林道を1キロ先に地道が簡易舗装路に変る所の空き地に駐車、駐車地の裏が登山口とある」 実際走ってみた感じでは、最初の橋を渡り左へ左へと曲がりながら奥へ入り次の橋で右へ曲がったように思う。この林道は、かなり長くて枝線もあり、カーナビを見ていてもこの橋まで来るのはなかなか分りにくい。 かもしか荘から2キロほど先の深山橋を左折れ白倉谷林道に入る。案内本には「深山橋東から4キロ先で橋の架かる分岐で右折れして橋を曲がる。それから先は清水ケ谷に沿った林道を1キロ先に地道が簡易舗装路に変る所の空き地に駐車、駐車地の裏が登山口とある」 実際走ってみた感じでは、最初の橋を渡り左へ左へと曲がりながら奥へ入り次の橋で右へ曲がったように思う。この林道は、かなり長くて枝線もあり、カーナビを見ていてもこの橋まで来るのはなかなか分りにくい。橋から先は、記事に書かれていた当時とは違い、道はかなり荒れていて四輪駆動車でないとかなり苦しい。駐車地も何度か切り替えし方向転換したので、始めて来た人には登山口まで来るのが難解であろう。ぶっつけ本番で来る人は先ず居ないだろうが、登山口が何処にあるのか探すのに大変のような気がした。 登山口は、駐車地の裏が山道の取り付きで、藪の切り開きから植林に入る。尾根に乗るまでは、木の根っ子を掴みながらの急登である。鹿除けのネット沿いに上って行き右手に深い植林、左手に二次林が拡がり尾根が合流する場所になると積雪も深くなってきた。ここからは緩やかな道となり幅の広い快適な尾根となる。植林を抜けるところは、冷たい風が容赦なく吹きつけている。ここでワカンを付け防寒具を着る。左手のカヤトの開きに入り葦や潅木の間を蛇行しながら尾根の高所に来るが、上の方はガスっていて見えない。体感気温マイナス4℃位か、雲の動きが早く荒れ模様でこれから先は、強風と寒さに耐える雪中行軍が始まった。ーーー  デジタルカメラも外に出していると電池が機能低下し動かないのでカメラをザックの中にしまう。低い笹原に変り、行く先にコブも見えるのだがガスの動きが早くてどれが清水の頭が良く分らない、尾根を南へ回り込んだ所でやっと清水の頭ということが分った。南雨乞岳は半分ほどしか見えない。冷たい風の吹きさらしの尾根から少し下のところで昼食。にぎり飯は凍っていて味がない、ポットの湯でインスタントラーメンを造り食べると体がピリッとする。温かい物は何よりのご馳走だ。隣にいた女性の方からの差し入れ、一寸した手作りの味にいつもながら感心させられる。 40分ほど経過したら、荒れ模様の天気が急に回復してきた。今日は強風とガスでダメかと誰もが諦めていたのだが、これから登る南雨乞岳や稜線が見えるではないか。皆、大喜びで元気に立ち上がり出発する。20分程で南雨乞岳に着く。風もおさまりなんと太陽も顔を出したので、気温も上がり絶好の雪遊び日和となる。カメラだけ持って雨乞岳へ登ることにした。この雪原、3月にしては残雪の多いホワイトヒルの中を鎌ケ岳や御在所ケ岳を眺めながら一歩一歩前へ進む。やがて頂上に着くと我々を歓迎するかのような大展望が拡がっていた。ーーー、伊吹山が御池岳のデカイ尾根が藤原岳へと続く、比良の山々も遠くまで澄んでいた。 冬山の厳しい道のりを制覇したものだけに許される光景だ。予定を変更してこの山(南と本峰の頂上で)に愛着が出て1時間以上も居座った。この大景観を再び見られる日はいつのことか。 下山は、南雨乞岳から南の尾根を10分ほど尾根が少し広くなった所で、左折れ(直進は大納言方面へ)深い笹を掻き分け西へ急降下する。右へ周り込みながら尾根へ取り付くのだが、少しズレても潅木で前が見えないので谷のほうへ迷い込んでしまいそうな場所だ。尾根に乗ると一本道であるが、明瞭な道がないので尾根芯を外さないように歩く。次第にシャクナゲが群生し頭や目に枝があたり歩きにくいヤセ尾根である。下降するに従い自然林に変わると支尾根に入り植林の山道へと続く、カヤトの草原に出て林道に出る。右折れして林道の駐車地に向かう。 |
| 【登頂アルバム】 |
 尾根の高所に出ると寒風が吹き荒れていた。防寒着・ワカンをつける。 尾根の高所に出ると寒風が吹き荒れていた。防寒着・ワカンをつける。 |
 ガスが消えたり出たりする厳しい尾根道をアップダウンしながら厳寒の清水頭に向かう。 ガスが消えたり出たりする厳しい尾根道をアップダウンしながら厳寒の清水頭に向かう。 |
 左斜面に少し下りた場所で昼食を済ませたら、ガスが消え天候が急回復し清水頭が見えた。ツイている日はこいうこともあるのだ 左斜面に少し下りた場所で昼食を済ませたら、ガスが消え天候が急回復し清水頭が見えた。ツイている日はこいうこともあるのだ |
 上の場所から反対側を見ると南雨乞岳が見えた。 上の場所から反対側を見ると南雨乞岳が見えた。 |
 南雨乞岳途中から見た、清水頭と綿向山。 南雨乞岳途中から見た、清水頭と綿向山。 |
 南雨乞岳稜線から見た東雨乞岳。 南雨乞岳稜線から見た東雨乞岳。 |
 南雨乞岳稜線から見た鎌ケ岳から仙ケ岳方面。 南雨乞岳稜線から見た鎌ケ岳から仙ケ岳方面。 |
| 南雨乞岳稜線から見た鎌ケ岳から仙ケ岳方面 |
 雨乞岳山頂から見た御在所岳、鎌ケ岳。 雨乞岳山頂から見た御在所岳、鎌ケ岳。 |
 左、雨乞岳山頂の東から見た北斜面。 左、雨乞岳山頂の東から見た北斜面。下、 雨乞岳山頂からイブネ・クラシと背景は伊吹山から御池岳から藤原岳へと続く大展望に酔った。 |
 |