 |
 |
| 【山記録】 |  |
||
| 日時・天候 | 2006年06月04日(日)・晴 | ||
| 山名・標高 | 芹川南尾根と向山(670m) | ||
| 山域 | 鈴鹿 | ||
| コースタイム |
県道向ノ倉口(08:20)〜向之倉(09:05-15)〜杉峠(10:05-15)〜P627(10:42)〜P657鞍部(11:20-12:20)〜P597(12:40-45)〜杉峠(13:30)〜向山(14:10-20)〜桃原(15:35)〜県道向ノ倉口(16:50) ●総タイム8時間30分(休憩タイム90分程度含む) |
||
| 距離/累積高度差 | |||
| 人数等 | iygsuzuka28人 | P657付近畑跡 | |
| 【軌跡ログ】 |
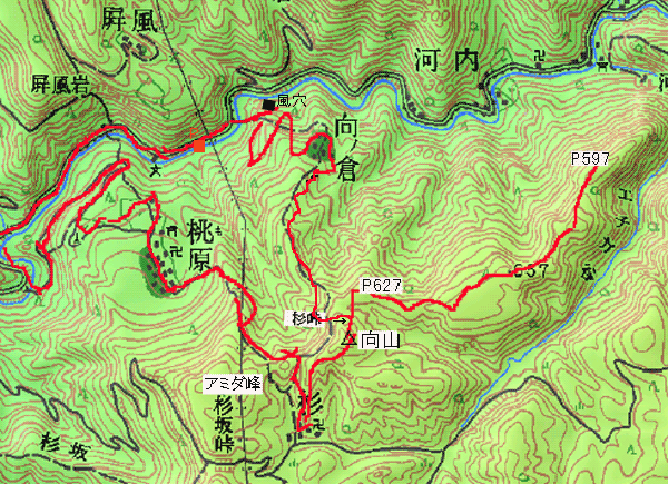 |
| 【足跡】 |
| <謎の集落> 近江と伊勢が交易していた頃。 人は、鈴鹿の山を生活の場として自然と共生してきた。 今だ、多くの謎があるとか。登山コースに出てくる「向ノ倉・向山・桃原」に関する記述も興味深い。 P657付近人工物の痕跡あり、こんな厳しいところで畑をしていたかと思うと驚愕。 それらを知って歩くと別の楽しみ方がある。 <県道17号線> 県道17号線河内方面へ車を走る。 向ノ倉は、芹川左岸なので橋を渡らなければならない。2軒建っている家の前で農作業をしていたお祖母さんに道を尋ねる。 ●向ノ倉へ行きたいのですが、 ○ここも向ノ倉だ。 ●集落があると聞いているのですが、 ○今来た道を少し戻って橋を渡り2キロほど先に向ノ倉の集落はある。あそこは人は住んでいない 何にしにいくんだ。」 ●杉峠へ行きたいのです。 ○山へ行くのかマムシやヒルに気を付けなされ」と教えてくれた。 どうやら集合地を通り過ぎたようだ。 仲間は、橋の手前の県道沿いの空地に集まっていた。 <集合地出発> 8時20分駐車地出発。 小さな橋を渡ると左手の道100メートルほど先に風穴があるので、寄り道をする。 入り口は狭いが中に入ると大人が立って入れた。 車道をジグザグに歩くこと30分ほどで向ノ倉に到着。 少し離れた右方向の広場に崩壊した家が見える。 車道の左奥にある井戸神社に立ち寄る。今は別の所に移転した。 参道には大きな鳥居が二つ倒れたままになっていた。登山の安全を祈願し、広場に戻る。左手の山てから裏道に入る。 裏道を行くと登り尾の道につながる。45分で杉峠に着く。 <向ノ倉(むかいのくら)> 向山の北麓、尾根の中腹に流されまいと必死にしがみつくような小さな山村がある。 芹川沿いの県道からもこの上部に村があるとは信じられないほどの山地である。耕地を持たずもっぱら薪灰の生産にたよっていたので離村を早めた。 村の環境立地条件は、脇ケ畑、霊仙地区を通じて最も悪条件であった。江戸末期には人口142人昭和44年に廃村となった。杉峠に向かう道は、谷道と登り尾があり途中で合流している。このうち「登り尾」は、現在も良好な状態が保たれ西方の展望も優れている。(鈴鹿の山と谷記述) <向山> 向山(670メートル) 杉峠の西のピークを言う。仙人の命名らしき名。登っておもしろい山でなく展望もない。北面の急斜面は迫力がある。著者(西尾寿一)の推測によると、向山という名は、一ピークではなく一連の山地に対して呼ばれる性格のもの。つまり向山は「杉峠から河内宮前に至る長大な山稜ではないか」との説である。 <桃原・茂原> 縄文時代から自給自足をしていたとか。元禄時代には366人もいた。現在は10戸程度。「風通し展望も」良い。高原的な環境は、避暑をかねた帰村者もいるとか。 建物は、古さを感じない。誰もいず不気味なほどの静けさだった。 |
| 【向之倉への道】 |
  左、向ノ倉への道。 左、向ノ倉への道。橋から歩いて30分程で向ノ倉へ着く。 高度を上げると芹川や甲頭倉方面が開けてきた。 右、風穴。河内風穴に続いているのではとの冗談を言いながら中に入る。 |
| 【井戸神社】 |
  左、井戸神社のカツラ。滋賀県指定自然記念物。H3.3.1指定。樹齢推定400年。幹11.6cm、高さ39m 井戸神社(多賀大社の末社)の境内に聳える県下最大級の巨木で主幹より大小の12本の幹に分かれ株立している。 右、井戸神社 蛇にまつわる伝説あり。 |
| 【向之倉】 |
   左、向ノ倉集落。明るい広場で家が数軒あったようだが、倒壊していた。 中、車道の終点。左上を上がると倒 壊した家屋を過ぎ、左方向に山道。 |
| 【登り尾から杉峠】 |
  左、杉峠の大杉。 樹齢400年推定。大杉の根元には石仏があり。 杉峠は、吉ケ谷の源頭にあり、通行の目印となっている右、登り尾。 車道終点の広場を左上を上がると、少し先に神社や倒壊した家の前を通り、道が上へと続いている。登山路は、昔人の生活道路につき、石積などの痕跡あり。 |
| 【P627付近を行く】 |
  P627の尾根は、二次林が美しい尾根を楽しみながら歩く。 P627の尾根は、二次林が美しい尾根を楽しみながら歩く。 |
| 【P657付近】】 |
   左、P657手前は明るい二次林の美しき森が続いていた。P657付近は人工物の痕跡あり。 左、P657手前は明るい二次林の美しき森が続いていた。P657付近は人工物の痕跡あり。中、時間の都合で鞍部で昼食。 右、ヌタ場。メダカが泳いでいた。 |
| 【P597】 |
  P657鞍部で昼食を済ませて、リュックを置いてP597まで行って見る。 この先はキレて河内風穴エチガ谷下流へ落ち込んでいる。直ぐ先はガケ見たい。 |
| 【帰路P627手前の鞍部】 |
  P627付近往きは尾根伝いに歩いたが、帰りは鞍部に下る。新鮮な緑が一杯あり、長めの休憩をとる。 |
| 【向山】 |
  杉峠の西のピークを言う。仙人の命名らしき名。 杉峠の西のピークを言う。仙人の命名らしき名。登っておもしろい山でなく展望もない。 北面の急斜面は迫力がある 著者(西尾寿一)の推測によると、向山という名は、一ピークではなく一連の山地に対して呼ばれる性格のもの。つまり向山は「杉峠から河内宮前に至る長大な山稜ではないか」との説である。 |
| 【杉集落】 |
  標高600メートル脇ケ畑のノ西の玄関口をなす石灰岩カルスト台地上にあるこの村は、いつの頃から存在するのか不明。 標高600メートル脇ケ畑のノ西の玄関口をなす石灰岩カルスト台地上にあるこの村は、いつの頃から存在するのか不明。「多賀明神のご神木を守る人々の子孫との」説もあり、杉という村はただならぬ由来を秘めているとのこと。 |
| 【桃原・茂原】 |
  |
  桃原。 桃原。右写真のカーブに下山。蛭がいないか靴を脱いで確認している。 建物は、古さを感じない。誰もいず不気味なほどの静けさだった |