 |
 |
| 【山記録】 | |||
| 日時・天候 | 2014年 03月24日(月)天候晴 |  口割山627.6m三角点 |
|
| 山名・標高・区分 | 栗ケ谷山(615.8m)・口割山(627.6m)・羽下谷の高(603m)/伊勢近辺 | ||
| 山域 | 三重・大紀町 | ||
| 交通 | 伊勢市から大紀町まで伊勢・紀勢高速道で50分。 | ||
| コースタイム |
駐車地・墓地(8:50)~75鉄塔(9:35-45)~栗谷山(10:30-40)~口割山(11:10-15)~P604(11:40)~本郷山(11:55-12:00)~71号鉄塔(12:15-昼食-13:10)~羽下の高(13:20)~作業道出会(13:30)~山道入る(13:45)~横谷三角点(14:30)~山の神登山口(14:50) ●総タイム6時間00分 ●コースタイム4時間15分程度(休憩90分ロスタイム15分) |
||
| 距離/累積高度差 | 沿面距離8.2km 累積高度+808m-776m(GPSデータ90%の数字) |
||
| 団体名・人数 | 単独 | ||
| 【足跡】 |
| 奥伊勢「大紀の山々」(小野幸年著)に掲載されている三ケ野三山(口割山・栗谷山・羽下の高)登山地図」を参考に歩いた。ブックによると、大内山側からも三山へ登る道はあるが縦走するとなると三ケ野側の方が移動が少なくて済むらしい。 往路は、鉄塔コース。復路は、口割谷南尾根(山の神)コースと決めた。 駐車地は、直ぐに分かったが鉄塔コースの登山口を間違い下山口へいったので15分ロス。 駐車地に戻り地図を確認する。近道のヤブ尾根を登っていくことにした。 100mほど登り伐採地に出ると、鉄塔尾根が見えた。 上部に76号鉄塔、谷底に三ケ野や錦小屋辺りが見え絵になる眺めだ。 駐車地から1時間近く歩いて75号鉄塔に来た。 ここからは、稜線に建つ71号鉄塔まで山肌を削った後に送電線が繋がっている。 71号鉄塔は、小さいながらも確認はできる。 左はこんもりしたコブは羽下の高辺り。右は、P604から口割山へ延びる山並みは登行欲のわく景観である。 さて、「羽下の高」の呼び名だがブックに「はげのたか」とある。ユニークな名だ。 75号鉄塔から先は、テープのある「鉄塔コース」に合流する。 植林と雑木の尾根で踏み跡のある坂である。75号鉄塔から45分を要し栗谷山に到着した。 山頂は、大きなシイや樫の木に覆われ展望は効かない。狭い空間地ながらも天井は明るい。 二等三角点標石と山名札が二つ木の枝にぶら下がっていた。 比較的広い尾根を30分歩いて口割山に到着。 ここも、栗谷山と同じような雰囲気で長休みはしづらい。 口割山からも先も広い尾根で踏み跡は明確である。猪が堀り起こしたと見られる荒れた山道が続く。この辺りは、地籍測量した黄色や青色の境界杭が打たれている。 P604は、標高差を余り感じない。山名札が二つぶら下がっていた。 「芦谷の頭」と「本郷山東峰」という名札である。 この山の雰囲気から見てP604が分かりよいと自分は思う。 西峰の本郷山へ寄り道をすることにした。 15分ほどで本郷山に到着。 ここも樹林の中の空間地である。「本郷山イセaok」と書かれた名札が一つぶら下がっていた。 足元を見ると、「地籍図根」と書かれた立派な三角点標石がある。 初めて見たのでとても新鮮な気持ちにさせられた。 国土地理院が設置したものかどうか分からないが、設置されてからまだ新しいような感じもする。 それにしても近年発売された奥伊勢大紀の山々(小野幸年著)に、「本郷山」のことや「地籍図根」の記述がないのが気になる。 12時15分、71号鉄塔に到着し昼食をとる。 71号鉄塔付近は、前の木が伐採され谷が開け送電線と鉄塔が一本の線となり谷底まで伸びているのが見える 弁当を食べ寝転ぶと青い大空が広がる。前は、遥か彼方山の上に小さい送電線の横に形の良い山は、大河内山が堂々としている。その尾根を辿ると立派な山容の有地山も逞しい。その後ろにオロチが顔を出している。 500m級の低山とは思えぬ風格を感じた。 下山路、1箇所間違いやすいところがあった。 |
| 【軌跡・山旅25000図87%縮小】 赤線は登り青線は下り |
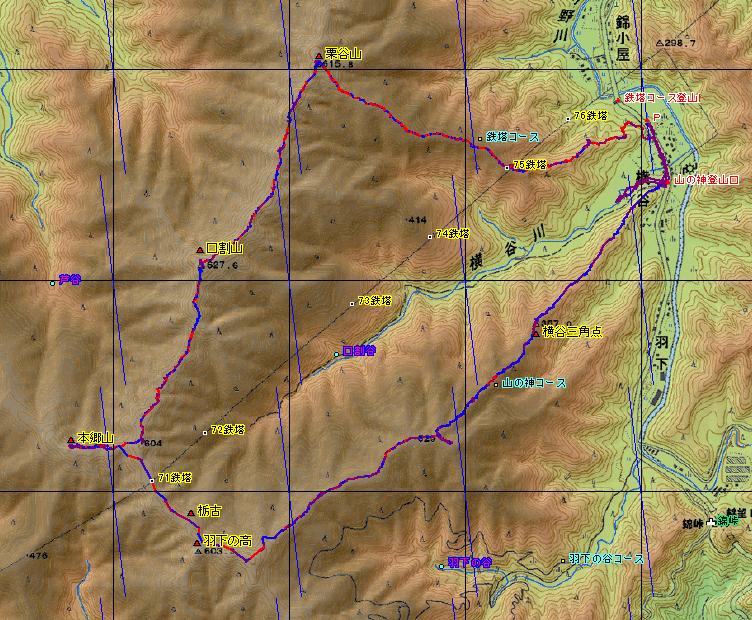 |
| 【鳥瞰図ー竹の谷山上空1660m上空から撮影】 |
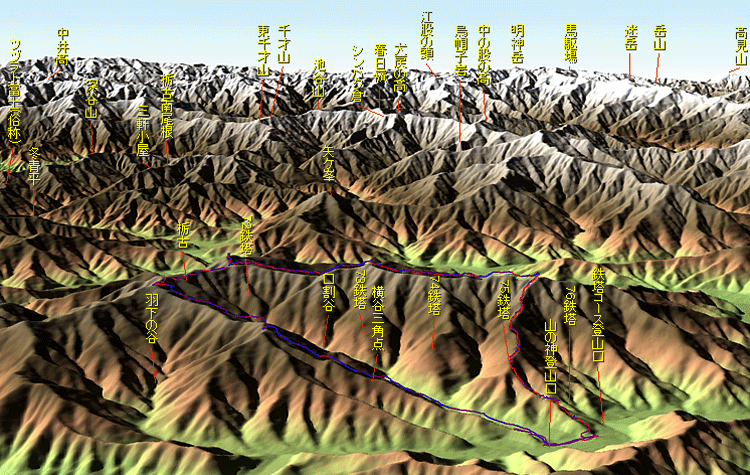 |
| 【駐車地】 |
  |
 上、横谷橋と横谷川。 上、横谷橋と横谷川。左、駐車地。 駐車地で登山の準備をしていたら地元の人がいたので登山口を尋ねる。 現地(横谷橋の袂)へ来て、地図を確認したら下山口ということが分かり再び駐車地まで戻り墓の裏から登ることにした。 |
| 【登山口】 |
 民家の裏から尾根に取りつく。 民家の裏から尾根に取りつく。鉄塔コースの登山口は、駐車地から更に200mほどいった所の林道から入ることことが後になって分かった。 |
| 【ヤブ尾根から76号鉄塔。下の集落は、錦小屋辺りか。】 |
 |
| 【75鉄塔からの眺め良し】 |
   上、75鉄塔から北東方面を見る。正面の山は、大河内山(545.9m) |
| 75鉄塔から西南方面の眺め(中央奥のピーク羽下の高、中央71号鉄塔、右にP604ピーク) |
 |
| 【75鉄塔から先は、テープのある登山道を歩く】 |
 左、植林。 右、雑木の尾根で歩きやすい。 |
| 【栗谷山】 |
  |
 山頂は、樹林に囲まれた中にあり視界はなし。 |
| 【口割山】 |
  |
 栗谷山から30分程で口割山に到着。 栗谷山から30分程で口割山に到着。ここも山頂は樹林に囲まれ展望は効かない。三角点あり。 山名札を見ると点名「芦ケ谷山」という標識もあり。 |
| 【尾根道は、猪が荒らした山道となってきた。地籍測量した杭あり。】 |
   尾根筋は、猪が荒らしたと思われる山道で荒れていた。 この辺の山道には、測量地籍の杭が打ってある。 |
| 【P604】 |
 P604には、 P604には、芦谷の頭と本郷山の東峰という名札あり。 地図を見ると、芦谷とは多少ズレているのような気もする?ー 本郷山の名はイセaoki氏の独自調査か。 ややこしいので統一してほしいものだ。 |
| 【本郷山に地籍図根あり】 |
  |
 P604から凡そ500m西に行くと小ピークあり。 P604から凡そ500m西に行くと小ピークあり。「本郷山」イセAOKIの山名札あり。 傍らに「地籍図根」と書かれている三角点石があった。 この標識を見たのは初めてである。 測量基準点のような気がする。 本日の収穫は、この「地籍図根」標石でした。 |
| 【71号鉄塔で昼食をとる。】 |
  |
 上左、南西の方角にあたる群界山か。 上右、北東にあたる大河内山方面。 左、本郷山とP604。 下、大河内山・有地山・オロチ山方面。 |
| 【71号鉄塔、全コース中一番の良い景観でした】 |
 |
 |
| 【栃古】 |
 栃古が羽下の高と勘違いしていた。 栃古が羽下の高と勘違いしていた。 |
| 【栃古から50m位下ると作業道あり】 |
  |
  羽下の高(603)は上右写真の高い地点にあることが後で分かった。 羽下の高(603)は上右写真の高い地点にあることが後で分かった。地図には載っていない作業道が高いところまで伸びていた。大紀の山本には、林道ではなく作業道と書かれている。300mほど行くと終点。ここから再び山道に入る。 |
| 【P529地点で間違う】 |
 間違ったポイント地点を写真に記す。 |
| 【横谷三角点】 |
  |
 山旅の国土地理院の地図は、357.0m です。 だが、ここにある3つの山名表示は全部357.3mとある。 近年、国土地理院の地図が修正? |
| 【山の神】 |
 山の神、隣にある地蔵さんの石碑には、「元文五年庚申」と刻まれている。 |
| 【山の神登山口に下山】 |
  |
 県道沿いに庚申さんあり。隣に山の神に通じる参道(階段)あり。 |