 |
 |
| 【山記録】 | ||
| 日時・天候 | 2008年06月07日(土)/晴・曇り |  |
| 山名 | 大笠山(1821.8m) | |
| 山域 | 石川・冨山県境 | |
| コース・タイム | 桂橋登山口(9:45)〜天の又(12:15-12:25)〜避難小屋(13:45-13:50)〜大笠山(14:30-14:40)〜避難小屋(15:25-13:30)〜天の又(16:35)〜桂橋登山口(18:30) | |
| 沿面距離 | ●沿面距離12.0km 標高差1200m | |
| 人数 | 関西shc16名体力度★★★★ 危険度★★(ガイド本による) | |
| 【軌跡図】 |
| 【鳥瞰図】 |
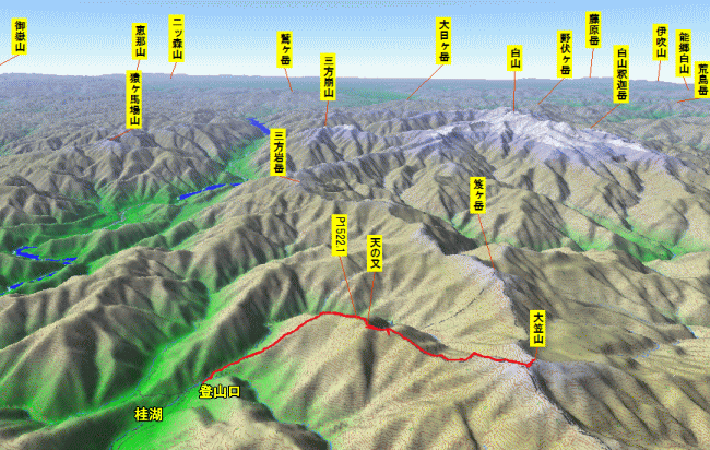 |
| 【足跡】 |
| 大笠山は、石川・富山との県境にある山で6月になっても残雪あり五箇山の奥深くにそびえる。 県営境川ダムの完成で日帰り登山が可能になった。 国道156線の楮橋(こうずばし)の手前で右 折れし、長いトンネルを抜けてダムサイトに出る。国道から約5キロである。桂湖は、美しいダム湖で広い駐車場がある。その先に湧水を引いた小公園があり、さらに200メートル先に飛騨・加須良(かずら)への橋の袂に「大笠山登山口」の標識が立っている。 道路端に車を停める。 大畠谷に架かる吊橋を渡るといきなり急な岩壁で、鉄ハシゴ五本、それに鎖場もある。見下ろすと右側が境川の湖面、左側が大畠谷の湖面で、足元は切れ落ちている。フカバラノ尾根の始まりである。 稜線の登山道は、木の根っ子などの多い急登で1300メートル付近までは歩きづらい。辛抱あるのみである。1300メートル付近に来ると尾根が広く平坦になる。その平が終わるところから丸太造りの階段になり、1522メートルの「天の又」とよばれる平らなところに出る。正面にこれから登る大笠山が現れる。 「天の又」までの距離は、半分の3キロである。きつい登りで体力をかなり消耗してしまった。 この先小ピークを3つも越えていかねばならぬと思うとしんどい。ーー水と栄養分を補給し気力を奮いたたせる。仲間内には、体調がすぐれずリタイアする人もあらわれた。 ブナの美しい原生林を下って、次のピークへと進む。登りきったところは木もまばらで、360度の視界が得られる気持のよいP1552のピークに立つ。西南方向に笈ケ岳(おいずる)が、その奥に雪の白山がどうにか見えた。この辺りから雪田が現れ道はドロドロにコネて最悪。 しかし、登山道にはイワカガミ・カタクリ・ミツバオウレン・ショウジョバカマなどが雪解けで開花した。ツツジやタムシバも咲く花の山に満喫する。 小ピークを越え尾根の右側を巻くように行くと、丸太造りの避難小屋が現れた。周りはカタクリの群生していた。上から単独・少数グループの人たち10人ほどとすれ違う。 尾根北側の草付をトラバースすると、また丸太の階段があり積雪の県境尾根に出る。分岐点には標識あり。雪の広い平地なので帰路方向を間違いやすい。(足跡がほうぼうにあった) 大笠山頂には一等三角点がある。 ガスで視界なし。長い無用早々に退散する |
| 【登山口付近】 |
 |
| 【吊橋】 |
  |
| 【P1552から笈ケ岳山を見る】 |
 |
 上の写真、 上の写真、白山の一部を拡大する。 |
| 【避難小屋】 |
  左、避難小屋から見た大笠山山頂。 右、避難小屋。山頂まで一時間。 |
| 【帰路、雪渓に要注意】 |
 避難小屋から40分ほどで稜線(県境尾根)に出る手前の雪渓。 避難小屋から40分ほどで稜線(県境尾根)に出る手前の雪渓。帰路は、迷いやすいので要注意。 |
| 【咲いていた花木】 |
   |
   |
   |