 |
 |
| 【山記録】 |  蕎麦粒山三角点 |
|
| 日時・天候 | 2013年09月28日(土)晴 | |
| 山名・標高 | 蕎麦粒山(そむぎやま)・1296,7m | |
| 山域 | 岐阜県奥美濃 | |
| コース・タイム | 西俣出会(7:20)〜930(8:20-30)〜P1076(9:40)〜蕎麦粒山(10:50-昼食-12:20) P1075(13:00)〜P994(13:30-40)〜西俣谷出会(15:00) 総タイム7時間40分。 ●コースタイム(上り3時間30分。下り2時間40分。) ●沿面距離9.1km ●累積標高(+1299m-1310m) |
|
| 人数 | 10人 | |
| 【軌跡図・山旅25000図】 |
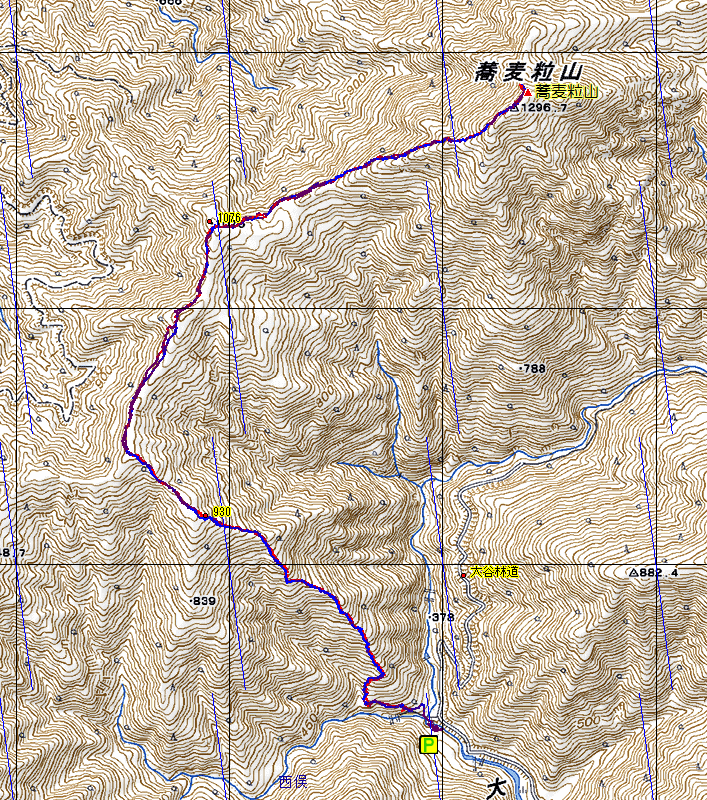 |
| 【足跡】 |
| <始めに> 奥美濃の名峰と云われる「蕎麦粒山は、三角錐をした特色のある山である。 夏は、ヤブがひどくて雪のある時期にしか登れないと聞いていた。 だが、今回ガイド役のIさん(名古屋市)は雪のない時期に西谷林道終点から登ったことあり。 林道が崩れていた(今も工事中)ので、手前の西谷出会いに車を留め林道終点まで1時間くらい歩いたとのこと。急斜面をロープや木の幹に掴まりながら這い上がる厳しいルートだったと話していた。 その後、新しく西尾根コースが整備されたので今回は新ルートからの挑戦である。 遠方からの旅たちなので世話人の山友Kさん宅(甲賀市)に泊めてもらう。メンバーは、顔なじみの山仲間である。 だが、大チョンボをしてしまった。 ホームページに必要な用具(カメラ・GPS・地図)を入れたバックを車に積み忘れてきた。 アップは、半ば諦めていたのだがKさんからアップして欲しいとのことから写真とGPS軌跡図が送信されて来たので、ホームページを作成することにした。 とのことから借り物ということでご理解願います。 <9月28日> 午前5時半に甲賀のK氏宅を出発。 午前7時前、集合地の岐阜県揖斐郡坂内村「道の駅」に到着。 7時10分、登山口の西谷出会に到着。 登山概要は、下記のとおり。 |
| 【西俣出会に駐車】 |
  |
 駐車地から西俣の広い河原へ降りて行くが、 周辺には 駐車地から西俣の広い河原へ降りて行くが、 周辺には「登山口」の標識が見当たらない。 まだ、登山道としての認知はされていないようだ。 川を渡るとヨシに似た2m位もある背の高い川木を踏み超えていかねばならぬ厄介な河原である。 尾根の先端に取りつくまで100m ほどある。 |
| 【沢を渡る】 |
  |
 水量は、膝下10cm。 水量は、膝下10cm。流れが早いので滑りやすい。 飛び石伝いに渡れば何とか靴を脱がなくても渡れた。 |
| 【長い急登の尾根】 |
  |
 尾根の先端に来るとピンクのテープあり、踏み跡も明確になる。 尾根の先端に来るとピンクのテープあり、踏み跡も明確になる。 沢沿いに巻きながら尾根筋に来る。 標高480m付近から急な登りが始まる。 ここから、標高950mj付近まで、高度差470mを一気に登る。 |
| 【P930付近に来て緩くなり休憩】 |
  |
 休憩地点から三角錐をした蕎麦粒山 が望めた。 見事な三角錐だ。あそこまで頑張ろう 進路を北方向へとを変える。P1076への尾根筋の道は、背の高い笹を漕いでいく。踏み跡はあるが分かりにくい。 |
| 【P1076手前の鞍部付近に来るとブナの原生林か現る】 |
  |
 原生林の鞍部に来るとブナ林の大木が見られた。休憩して大木に触る。 冬は雪に埋まって歩きやすいとか。 この先のヤセ尾根は、雪庇が張り付いて非常に危険だったと経験者は語る。 |
| 【樹林の切れ間から見えた谷の先は黒谷か】 |
 |
| 【1100付近からは、急陵のヤセ尾根で体力を使う】 |
 ヤセ尾根は、シャクナゲや雑木のヤブで山頂付近まで続く。 尾根伝いに進めないので、巻いては尾根へ出る。次は、尾根筋下を歩いて尾根へ出る。この繰り返しである。シャクナゲ等の枝が山道を塞いで歩きにくい。 登りは、体力のいるヤセ尾根だった。 |
| 【360度の大展望を見ながら山頂で昼食】 |
  |
 苦しかった登りをクリヤした皆さん感激の笑顔でした。 苦しかった登りをクリヤした皆さん感激の笑顔でした。山頂からの展望。 西に金糞岳・三周ケ岳・笹ケ峰。 北に冠山・白山・能郷白山。 南に貝月山・天狗山など山また山の絶景でした。 |
| 【山頂からの展望ー正面に五蛇池山(1147.6)が大きく見える。背景は伊吹山】 |
 |
| 【下山は、往き来た道を戻る】 |
  |
 K氏が東ルートを探索に行く。木の枝が道を塞いでいるとの報告。 K氏が東ルートを探索に行く。木の枝が道を塞いでいるとの報告。 新ルートができてからは奥ルートから登る人は少ないようだ。とIさんはいう。 荒れているので、周回は諦め来た道を戻ることにした。 |
| 【花木】 |
  |
| 【西俣出会に戻る】 |
  |
 無事、戻ってきました。 無事、戻ってきました。最後に、 蕎麦粒山を歩いた感想。 ●登りがきついので体力を要する ●登山道は整備されたがヤブぽっいので一般道とは云ええない。 ●登山時期、シャクナゲの咲く頃。本命は、雪のある冬だが雪庇が気になる ●正面に見えた五蛇池山(1147.6)まで日帰り縦走は可能なのか。 |