 |
 |
| 【山行日誌】 |  |
|
| 日時・天候 | 2008年10月28日(火)・晴 | |
| 山名 | 地蔵岳(1432m)・天狗山(1432m) | |
| 地域 | 大峰前鬼(奈良県) | |
| コースタイム | 駐車場(7:00)ー登山口(07:18)ーP1180(8:30~8:40)黒谷の頭(9:20~9:30)ー(11:45~12:00)ー本谷(10:05~10:15)ー地蔵岳(11:50~12:30)ー奥守岳(13:00~13:10)ーしゃくなげ岳(13:50)ーP1472(14:00~14:10)ーP1224の先(14:40~14:10)ー駐車場(15:50) ○沿面距離 12.5キロ | |
| 所要時間 | 7時間50分 | |
| menber | Igazyuku 7人(男4女3) | |
| 【25000図軌跡】 |
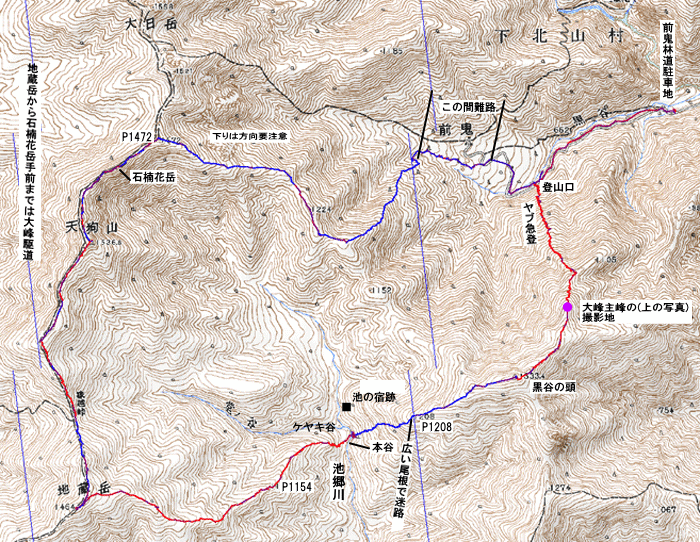 |
| 【鳥瞰図→R169号河合標高4200メートル上空から撮影】 |
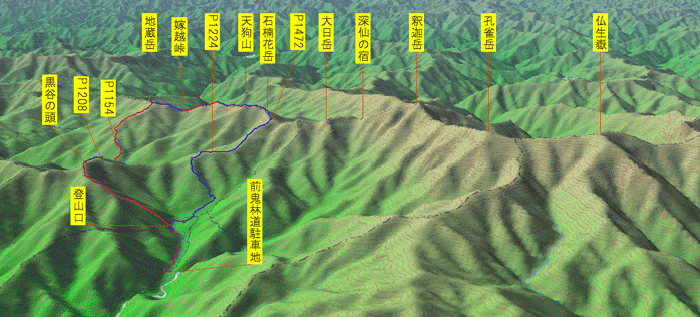 |
| 【山記録】 |
| 伊賀塾の「大峰池郷川源流の尾根を周回」山行きに参加した。 コースは、大峰・前鬼からヤブ尾根を上がり黒谷の頭へそこから一挙に本谷まで急降下する。 谷底から地蔵岳へ一気に登る。地蔵岳から天狗山までは大峯奥駆道を歩く。 尾根を直進し、P1472へ進む。そこから前鬼へ下山するプログラムである。 一般研修という言葉で参加したが、塾長との物差しがかなり違っていた。 かなりハードの道は、修験道の業であったが得るものも大きかった。 紅葉して羅漢を抱く釈迦ケ岳など大峰主峰の大展望が楽しめた。(トップの画像) 登山口の前鬼は、奥駆縦走のイメージが強いところである。 印象に残っことを列挙する。 ①今だ人間の匂いがしない未知なる山の環境が存在した。 ②その中に入るとブナ林が多くて明るい。 樹木は赤や黄色に染まり、下草のない枯れた大地に落ち葉が積もる。大地は、表現しがたいほど美しかった。 ③ブナの大木が倒れたまま沢山横たわっていた。ーー大木の墓場である。 「やがて自然に還り大地に芽を出している木もあった。 (歩いて邪魔ということはなく)どうぞそのまま眠っていてくださいーーという心境であった ④大木に熊が引っ掻いたと思われる傷痕あり、日本カモシカらしき動物の姿を何度も見た。 ピィーという声がこだました。森に邪魔者が入ってきたというお知らせです。ゴメンナサイ。 ⑤「登山口から黒谷の頭」・「本谷から地蔵岳への上り」は緩むところがない。ひたすらケモノ道らしき道を直に上がる。先頭についていけず苦しい。 塾長が、後ろからマイペースマイペースとの声がかかる。 「心臓は高鳴り、足は前に出ず」ーー テレビで某女性登山家が宣伝している。粉末を仲間にもらう。 水にを溶かしてい飲む。それが効いたのか何とか山頂へ辿りついた。 <復路> 下り道は、迷いやすい。 ポイント(P1224)までは、初めての者でもラクラクに来られる。これから先の下り尾根は複雑である。 後からGPSの軌跡を見てなるほど左へ左へと歩いたと分かる。 広い尾根では、左に寄り過ぎる可能性もあり経験者でないとその判断はできないと思う。 ここは、道らしきところがなく難路だった。 一発勝負は、危険。事前にルートを探索した方がベスト。 |
| 【前鬼林道の奥へと進み車止付近の空地に駐車する】 |
  前夜自宅を出発する。深夜、前鬼林道終点到着。空地に車を停めテントや車の中で寝る。駐車地は、奥深いところ。夜は、気味の悪いくらい静かでした。 翌日、5時過ぎ起床。7時出発 |
| 【登り口】 |
  車を停めたところから通行止め鎖をまたぎ、奥林道へと進む。 (右上の写真) 通行止め鎖のところから15分くらいで登山口に到着。左側の大木が目標。大木から20メートルくらい行ったところに防護壁がありその脇から登る。 標高差350m位角度は60度くらいの直登で喘ぐ。ドンジリでーー塾長がマイペースと励ましの声。 |
| 【黒谷の頭】 |
 標高差350m位角度は50度くらいの直登で喘ぐ。ドンジリでーー塾長がマイペースと励ましの声。 標高差350m位角度は50度くらいの直登で喘ぐ。ドンジリでーー塾長がマイペースと励ましの声。やっと黒谷の頭に来て大峰の山々が見え大感激(トップの画像)でした。 地蔵岳まで人の足跡を感じたのはこの標識のみ。しかも今月に登頂したとの記録あり。 |
| 【落ち葉が積もる広い尾根】 |
 落ち葉の美しいダダ広い尾根は、気持ち良く歩けたが、右と左に大きな尾根がある。 落ち葉の美しいダダ広い尾根は、気持ち良く歩けたが、右と左に大きな尾根がある。 |
| 【本谷】 |
 膝くらいまで水があり、靴を脱いで渡る。 膝くらいまで水があり、靴を脱いで渡る。下流はゴルジェで道具がないと進めないとか。 |
| 【地蔵谷への上りP1154付近】 |
 |
| 【地蔵岳近く来ると緩やかな上り】 |
  苦しみを抜けたら広い美しい大地が広がる。ここは、地上の楽園です。美しい大地に乾杯。 |
| 【地蔵岳】 |
  |
 |
| 【奥駈け道を行く】 |
 地蔵岳から天狗山までは、大峰奥駆道を歩く。 地蔵岳から天狗山までは、大峰奥駆道を歩く。紅葉の素晴らしい縦走路で心の中で御経を唱える。 キツイアップダウンも行者が歩いた道は楽に感じる。 |
| 【嫁越峠】 |
  嫁越峠から黒谷の頭が見えた。(左) お嫁さんがここを越して隣村へお嫁に行ったとの伝説。 昔の人は健脚だったんだ。 |
| 【上の写真を一部ズームアップする】 |
 |
| 【奥守岳】 |
 100キロを超える奥駆け道。 100キロを超える奥駆け道。今日歩いた道は、奥駈け道の中でも最高に良い場所と塾長の声あり。 何とラッキー。 |
 紅葉に染まる奥守岳の周辺。 |
| 【天狗山】 |
  |
| 【石楠花岳】 |
  |
| 【左、P1472。右、P1224】 |
  下り道。 このポイント(P1224)までは、初めての者でもラクラクに来られる。これから先の下りは複雑である。この尾根も変化があり美しい。 |
| 【尾根は複雑である】 |
 この先、どちらの方向へ行くのか。 この先、どちらの方向へ行くのか。塾長も右に左に確認しながら左の尾根を選ぶ。 普通に歩けば右の方向へ足が向くのだがーー |
 この先も難解だ。熊さんの糞らしきもの散らばっている。木を削ったあともあり。熊鈴ジャンジャンと鳴らそうとーー。 この先も難解だ。熊さんの糞らしきもの散らばっている。木を削ったあともあり。熊鈴ジャンジャンと鳴らそうとーー。前鬼林道へ下りるのも難しい。 |