 |
 |
| 【山日誌】 | ||
| 山名・ 山域 | 姫越山(502.9)座左の高(429.0) (三重・南伊勢町) |  姫越山三角点 |
| 日時・人数 | 2011年12月18日(日)・単独 | |
| 交通・駐車地・ 登山口等 |
伊勢市から県道伊勢南島線・国道260号線を走る。棚橋トンネルを過ぎたところで左折れ南伊勢町新桑寵(さらくわがま)へ。堤防下広場に車を留める。近くに登山口の標識が立つ。伊勢から1時間余。 | |
| コース・タイム |
駐車地(8:05)〜沢渡る(8:20)〜支尾根(8:50)〜展望所(9:50-10:00)姫越山(10:15-10:40)〜狼煙台跡(10:50)〜中電小屋(11:30)〜芦浜池(11:40)〜昼食と周辺散策(11:40-13:30)〜座佐の高(15:00-20)〜駐車地(16:30) | |
| 時間 | 総タイム 8時間30分(休憩タイム約2時間30分) 探索時間含む。 |
|
| 距離 | 12.8 キロ 累積標高+1610m−1517m | |
| 音楽 | 「浜辺の歌」 バイオリン千住真理子 | |
| 【軌跡図山旅改訂40000図】 |
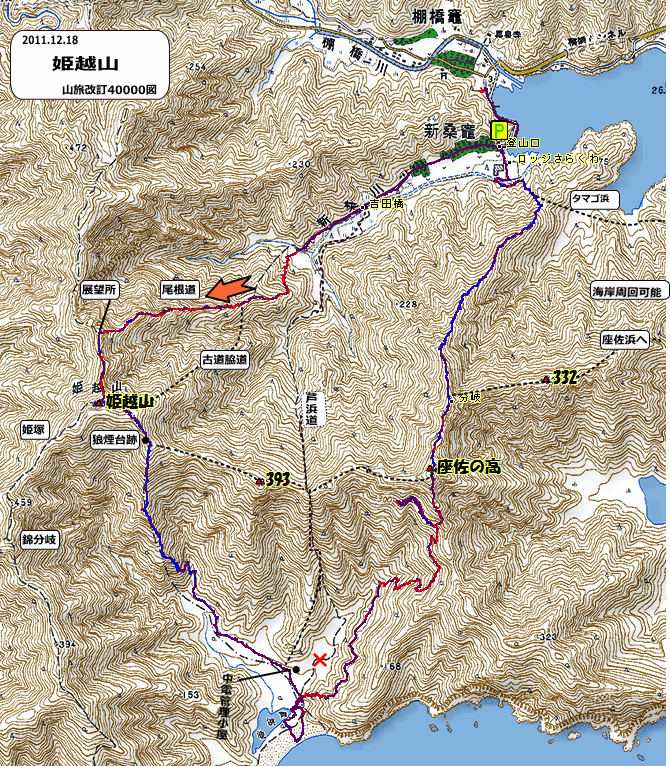 |
| 【足跡】 |
| 山友から姫越山の案内を頼まれていたので、下見を兼ね周辺を探索することにした。 今までは、大紀町錦から2回登ったことがある。 今回の登り口は、南伊勢町新桑寵(さらくわがま)である。 昔は、原発で揺れた南島町奥の小さな漁村。 今は、平成の合併で南伊勢町となり伊勢市の隣町。 アクセスの国道260号が改良され(伊勢から)1時間余りで行けるようになった。 錦から登るネット情報は溢れているが、新桑寵となると殆どなし地形図を頼りに歩くことにした。 登り口の新桑寵(さらくわがま)とは難しい名である。 以前、地元で教師(校長)をしていた人(Y氏)に「寵」という意味を教えて貰ったことがある。 それによると、 この地は人里から鎖され平家落人の隠れ場所に適していたようだ。 海から眺めたら鋸の歯のように見えるので地元の人は「鋸山」とも呼ぶ。 この地には沢山○○竈という地名あるが、その意味は「平家の落ち武者が塩を精製するのに使った窯から」この名か付いたと聞く。 姫越山は、502.9mと低山ながら海抜0メートル近くから登るので正味登らなければなない。 意外にも歩き応えのある山でもある。 南伊勢町側の登山路は、地元の南勢テクテク会さんがテープや標識が整備して頂いたのだろう。予想通り歩きやすかった。 姫越山に来ると、芦浜と芦浜池が見えた。 島が両側を挟むかのように前に突き出た弓型の海岸線が美しい。 小さな波が泡立ち行ったり来たりしているのを見ると地球が呼吸をしているかのようだ。 本当の良さは現場に来て初めて知る。 狼煙台跡から境界尾根を降り芦浜に来た。 芦浜池は、透き通るように美しい海跡湖だ。 まるでオアシスのような雰囲気を持つ。 反対側は、熊野灘である。 芦浜へ打ち寄せる波は静かで優しい。 アーチ形をした海岸線は天然の美である。 熊野灘のイメージとはほど遠い波静かな海岸でした。 海と湖の間に樹林帯がある。 松林でないのが、実に新鮮である。 外国にでもいるような感じがする。 芦浜は、厳しい山壁に囲まれた自然の要塞でもあり陸の孤島でもある。 今、原発が社会をぶち壊した。芦浜に原発はいらない。 |
| 【登山口付近】 |
| 左、堤防下広場。右、登山口に立つ「姫越山3.4k」の立札 |
  |
 左、登山口全景 左、登山口全景中央一番奥、少し頭を出いるのが姫越山。その右、高い山が狼煙台跡。中央、下から尾根が伸びている先がP393と思われる。 右、新桑寵集落を抜ける登り道。 左、「ロッジサワクラ」へ行く帰り道。 |
| 【吉田橋】 |
 吉田橋に来ると分岐あり。 吉田橋に来ると分岐あり。右の「尾根道」へと進む。 左は、芦浜池まで通じている「芦浜道」 |
| 【古道脇道と尾根道との分岐】 |
  |
 上左、川を渡ると標識あり山道に入る。 左、古道脇道と尾根道との分岐。右の尾根 をとる。 |
| 【尾根道】 |
  |
  |
| 【境界尾根に出て右折れすると展望所あり。ここから見た古和浦湾】 |
 |
| 【姫越山】 |
  |
 |
| 【狼煙台跡】 |
 源平合戦の頃の遺物。当時はここからの眺めが良かったことに違いない |
| 【境界尾根を下る】 |
  |
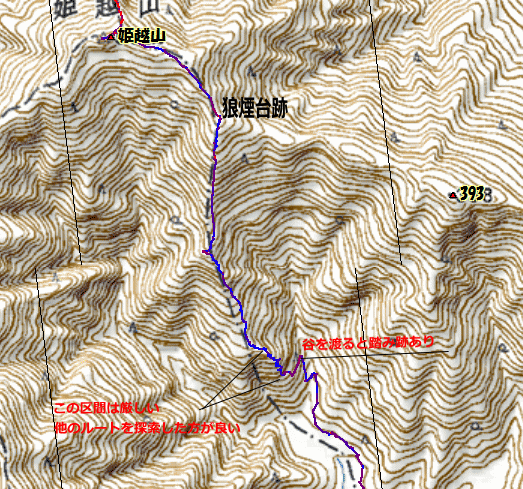 狼煙台跡から境界尾根を降りる。 狼煙台跡から境界尾根を降りる。中電の境界石あり。 テープも踏み跡もなし。時折道らしきところも現れたが直ぐに消えてしまう。 谷へ降りる手前が最も厳しい。強引に降りたが、ここは危険なので避けた方がよい。 地形図を見ると反対側の谷へ降りた方が無難なような気もするが、谷の様子が全く分からないのでコメントはできない。 芦浜池へ行くには、急がば廻れ正規のルート(芦浜道)で降りた方が安全だし早いと思った。 |
| 【谷を渡ると道が現れた】 |
  |
 谷へ降りると踏み跡あり。 谷へ降りると踏み跡あり。この谷の上流部を探索しなかったが、踏み跡がありそうな匂いもする。 |
| 【中電の作業小屋】 |
 管理小屋か作業小屋が分からないが、誰もいなかった。 管理小屋か作業小屋が分からないが、誰もいなかった。この一帯は中電が所有している土地なのだが、建物や立札に何故か、管理者「中電」という名がなかったのがとても気になる。 この小屋の前には、管で引き込んだ水か音をたてて流れていた。 |
| 【芦浜池ー湖の入口から撮影】 |
 |
| 【芦浜池。水面に映る山影】 |
 |
| 【芦浜池。湖の奥から撮影ー背景は姫越山】 |
 |
| 【浜と湖の中間にある森林帯】 |
  |
  |
 ハマナツメ群落の樹林は明るくて気持良い。松林でないのがとても新鮮だ。夏は涼しいだろう。 |
| 【芦浜海岸】 |
 |
| 【芦浜海岸】 |
| 余りにも美しい浜辺の芦浜海岸。 時の経つのも忘れ2時間も遊んでしもうた。 海の彼方から あの歌が聞こえてきた。 「あした浜辺にさ迷えば、昔のことおぞ偲をばるる 風の音よ波のさまよーー」 |
 |
| 【芦浜海岸】 |
  |
 |
| 座佐の高(さざのたか)への登り道は、余裕のない探索。 |
  |
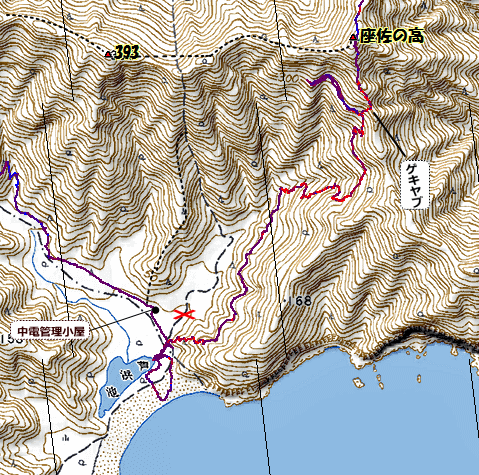 上左、「無断立入り禁止」のある標識のあるところから入る。 上左、「無断立入り禁止」のある標識のあるところから入る。上右、山道。左、軌跡図。 歩いた道にはテープや標識なし。山道は、整備され歩きやすい。「座佐の高」近くまで登る。軌跡の最終地点(左図標高300m地点)へ来ると下りとなったので、バックして上の尾根に近い接点を探す。 左図、「ゲキヤブ」のところを20mほど上がることにした。斜面は、シダやイバラや雑木が密生しとても上がれるようなところでないが、選択の余地なし。木枝や草を右に左に掻き分け前進するが1メメートル進むにも悪戦苦闘した。衣類は、引っ掻き穴があいた。ここへ来るまでに何度か分岐があった。何処かでP168の尾根に上がれたのだろうと思うが調べる余裕なし。それにしてもこの山道は、何処に続いているのだろうか。 |
| 【座佐の高の尾根に出ると芦浜と海跡湖kの芦浜池が見えた】 |
 |
| 【尾根の最後は急勾配となる。下の画像は、その手前】 |
  |
| 上の所から少し先に見えた。古和浦湾(上)と座佐浜(中)と海跡湖(下)の絶景。 |
 |
| 【座佐の高(ざさのたか)】 |
  |
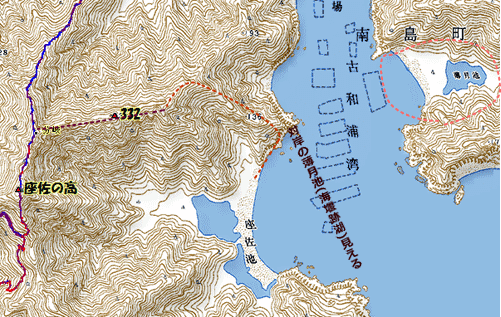 山頂からも座佐浜が見えた 山頂からも座佐浜が見えた座佐浜にも、芦浜と同じ海跡湖の座佐池がある。 案内板を見ると、対岸の薄月池(海跡湖)も見えるらしい。 探索したかったが、座佐浜まで2.7kそこから新桑寵まで2.9k合計5.6kあり。しかも海岸線の厳しいコブを乗り越えねばならぬ。只今の時間15時、決行すれば日が暮れてしまうので次の機会にしよう。 座佐の高から新桑寵(駐車地)まで2.キロの下り道。リュックの重み9キロから7キロ位まで軽くなったのに疲労でペースダウン1時間もかかった。 |
  |
| 【古和浦湾】 |
 |
| 【下山】 |
  |